ブログBlog

ブログ Blog
歯磨きについて
歯科治療について
2025/04/07

歯磨きは、私たちの口内環境を清潔に保つために欠かせない日常的な習慣です。
正しい歯磨き方法を実践することで、虫歯や歯周病を予防し、健康な歯と歯茎を維持することができます。ここでは歯磨き方法について説明します。
1. 歯磨きの目的
歯磨きの主な目的は以下の通りです
• 歯の表面の清掃
食べ物の残りかすや細菌の塊(プラーク)を取り除き、虫歯や歯周病を予防します。
• 歯周病予防
歯茎の健康を守り、歯周病(歯肉炎や歯槽膿漏など)の発症を防ぎます。
• 口臭予防
口腔内の細菌から発生する臭いを防ぐためには歯磨きが効果的です。
2. 歯磨きの準備
• 歯ブラシの選び方
歯ブラシは自分の歯や歯茎の状態に合ったものを選ぶことが重要です。歯ブラシのヘッドの部分が大きすぎないものを選びましょう。
歯ブラシの毛の硬さには以下の種類があります。
①やわらかめ(ソフト)
毛が非常に柔らかく、歯や歯茎に優しいため、歯茎に腫れや炎症のある方、歯茎が敏感な方に向いています。
②普通(ミディアム)
一般的に多くの人に適した硬さで、歯茎や歯を傷つけることなく効率よく歯垢を除去できます。
③かため(ハード)
毛が硬く、力強いブラッシングができるタイプですが歯茎やエナメル質を傷つける恐れがあるため、使い方に注意が必要です。
• 歯磨き粉の選び方
歯磨き粉はフッ素が含まれたものを選ぶと良いでしょう。フッ素は歯の再石灰化を助け、虫歯を予防する効果があります。
フッ化ナトリウム・フッ化第一スズ を含む歯磨剤です。幼児から高齢者まで生涯を通じて家庭で利用できる身近なフッ化物応用で、世界で最も利用人口が多いです。
日常的に適量のフッ化物配合歯磨剤を使って歯みがきをすることにより、口腔内にフッ化物を供給し、むし歯を予防します。
成人・高齢者の根面むし歯に対しても、67%の予防効果があるとの報告をはじめ、多くの研究が重ねられており、根面むし歯の予防においても効果があります。
•デンタルフロス
デンタルフロスは、歯と歯の間のプラーク(歯垢)を取り除くための細い糸です。歯ブラシだけでは届かない歯と歯の間や歯周ポケットの清掃に役立ちます。フロスを使うことで、虫歯や歯周病の予防に効果的です。
使用方法として、ロールタイプのフロスの場合はフロスをおよそ40センチほどの長さに切り取り、(目安は指先から肘までの長さ)左右の指に巻きつけて、歯間に優しく挿入し、前後に動かして汚れを取り除きます。少しずつ指に巻きつけた糸をずらして使っていきます。歯肉を傷つけないよう、優しく使うことが大切です。力を入れて歯間に押し込まないように注意しましょう。
デンタルフロスには、ロールタイプのものや、ホルダータイプのものなど、さまざまなタイプがあります。初めて使う方にはホルダータイプが使いやすくておすすめです。ロールタイプは慣れてしまえば簡単で経済的ですので自分に合ったものを選んで、毎日使うようにしましょう。
•歯間ブラシ
歯間ブラシは、歯と歯の間を清掃するための小さなブラシです。デンタルフロスと同じく、歯ブラシでは届かない場所を清掃するために使われますが、フロスよりも簡単に使えると感じる人も多いです。歯間ブラシは、ブラシのサイズが複数あり、歯間の広さに合わせて選びましょう。
歯間ブラシの使用方法は、ブラシ部分を歯と歯の間に軽く挿入し、前後に動かして汚れやプラークを取り除きます。
また、歯間ブラシは歯茎にも優しく、フロスよりも扱いやすいため、歯周病の予防や歯垢の除去に有効です。
特に、矯正器具をつけている人や、ブリッジやインプラントがある人にもおすすめです。
歯間ブラシを使う際は、歯間の広さに合ったサイズを選ぶことが重要です。無理に大きなサイズを使うと歯や歯茎に負担をかけることがあるため、注意が必要です。
3. 歯磨きの方法
歯磨きは「力を入れてゴシゴシ磨く」のではなく、優しく振動させるように丁寧に磨くことが重要です。
<歯ブラシの持ち方と角度>
• 持ち方
歯ブラシは鉛筆を持つように、軽く持ちます。力を入れすぎないようにして、歯や歯茎に負担をかけないように心掛けましょう。
どうしても強く力が入ってしまう場合は歯ブラシの根元ではなく先の部分を持って磨くと力が軽減されます。
• 角度
歯ブラシを歯と歯茎の境目に対して45度の角度で当てます。この角度でブラシを動かすことで、効率よく磨く事ができます。
<歯ブラシの動かし方>
歯ブラシを歯の表面に軽く押し当て、細かく振動させるように動かします。強い力でゴシゴシ磨かないように注意しましょう。
歯茎と歯の境目にブラシを当てて、歯垢を除去するイメージです。力を入れすぎず、優しくブラシを振動させましょう。
歯の外側、内側、噛み合わせ面をしっかり磨きましょう。
<歯磨きの順番を決める>
磨く順番を決めておくと、全体をバランスよく磨きやすくなります。例えば、上の歯から始めて、次に下の歯を磨くというように順番を決めましょう
•歯間を磨く
歯と歯の間は、歯ブラシでは届きにくい部分です。フロスや歯間ブラシを使うと、より効果的に清掃できます。
•歯の外側から内側へ
歯の外側(頬側)を先に磨き、次に内側(舌側)を磨きます。外側を磨くことで、目に見える部分をきれいに保ち、内側を磨くことで食べかすをきちんと取り除けます。
歯ブラシを歯の表面に当て、優しく小刻みに動かします。力を入れすぎないように注意しましょう。大きな動きでゴシゴシ磨くと歯や歯茎を傷つける事があります。
下の歯の内側は特に磨きにくい部位です。舌に近いため食べかすが溜まりやすいので、しっかりと奥歯から磨くことが必要です。
•歯のかみ合わせ面を磨く
歯の噛み合わせる面(噛む部分)を磨きます。ここには食べ物のカスや細菌が残りやすいため、念入りに磨くことが大切です。
磨くときは、歯ブラシの毛先を歯の溝に押しあてて前後に小さく動かします。大きく動かすと溝の中に毛先が届かないので磨き残しの原因となります。
4. 歯磨きの頻度とタイミング
•1日3回の歯磨き
食後の歯磨きが基本的です。特に寝ている間は唾液の分泌が減少し、細菌が繁殖しやすいため、夜は寝る前にしっかりと磨くことが大切です。
5. 歯磨き後のケア
口腔ケアアイテムの使用
•マウスウォッシュ
口臭予防や歯周病予防に役立ちます。
•フッ素洗口液
口腔ケアを目的とした製品で、フッ素を含んでいる液体です。フッ素は歯を強化し、虫歯予防に役立つことで知られています。
6. まとめ
正しい歯磨きは、歯と歯茎を健康に保ち、虫歯や歯周病を予防するために不可欠です。歯ブラシを正しく使い、優しく丁寧に磨くことが大切です。
また、フロスや歯間ブラシを併用して、歯と歯の間も清潔に保ちましょう。歯磨きは日々の習慣であり、正しい方法を身につけることで、将来にわたって健康な口内環境を維持することができます。
あなたへのおすすめ記事
-
-

- 歯科治療について
- 小児矯正はいつから始めるべき? ~後悔しないためのタイミングと考え方~
-
-
-

- 歯科治療について
- 赤ちゃんから始めよう!歯と骨の健康を守るフッ素
-
-
-
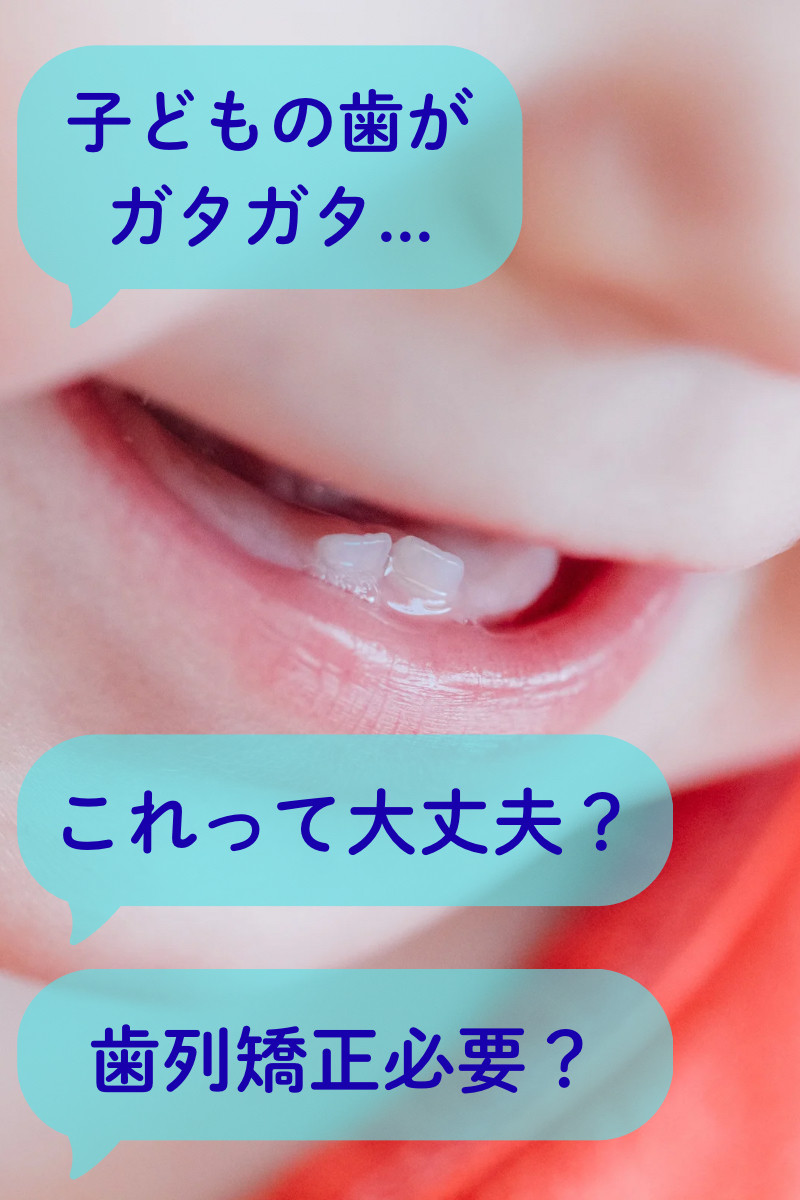
- 歯科治療について
- 子どもの歯がガタガタ…これって大丈夫?矯正は必要?と不安な親御さんへ
-
-
-
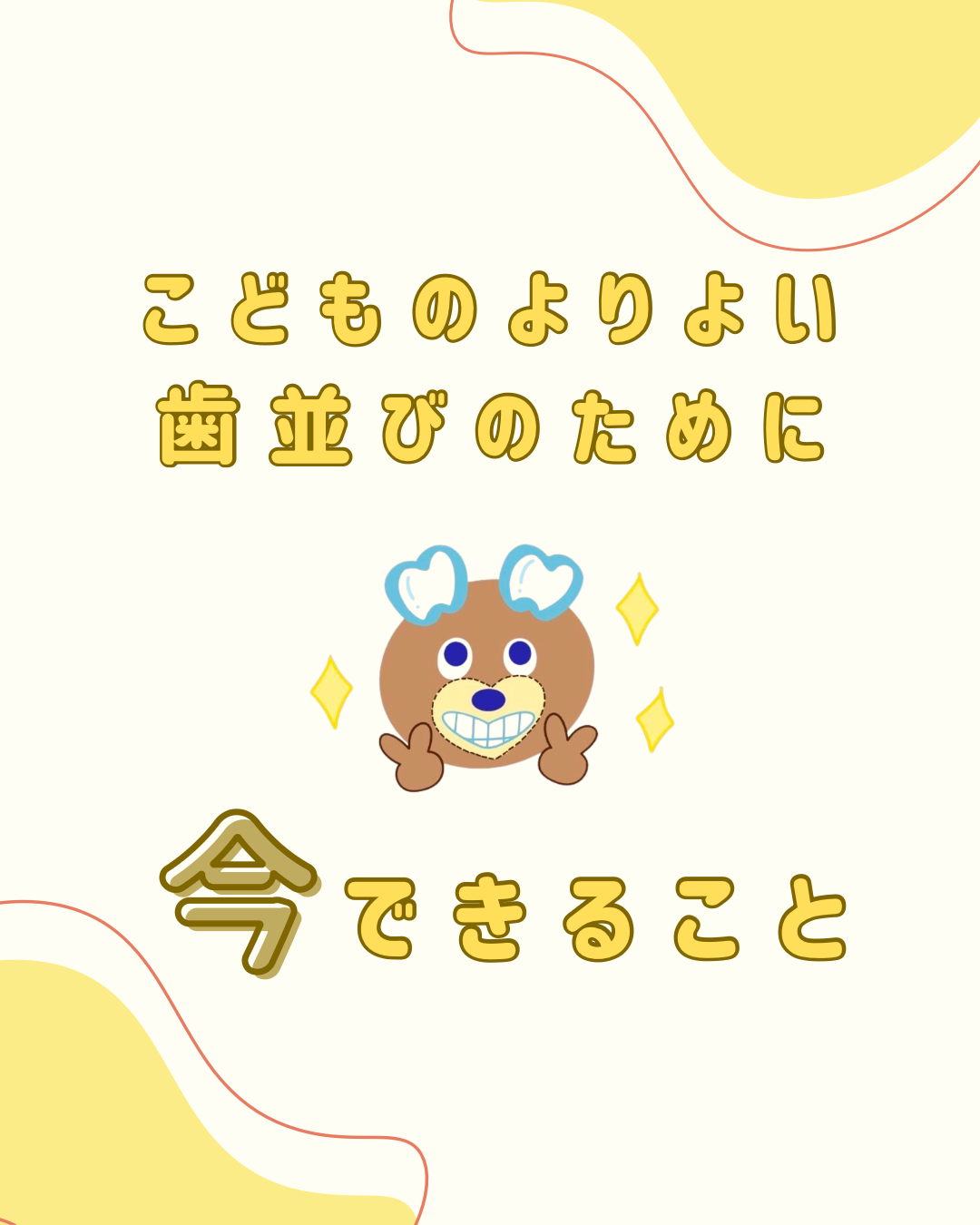
- 歯科治療について
- こどものよりよい歯並びのために今できること
-
 電話する
電話する WEB予約
WEB予約

 0798-65-5611
0798-65-5611
