ブログBlog

ブログ Blog
医療費控除について
歯科治療について
2025/03/31
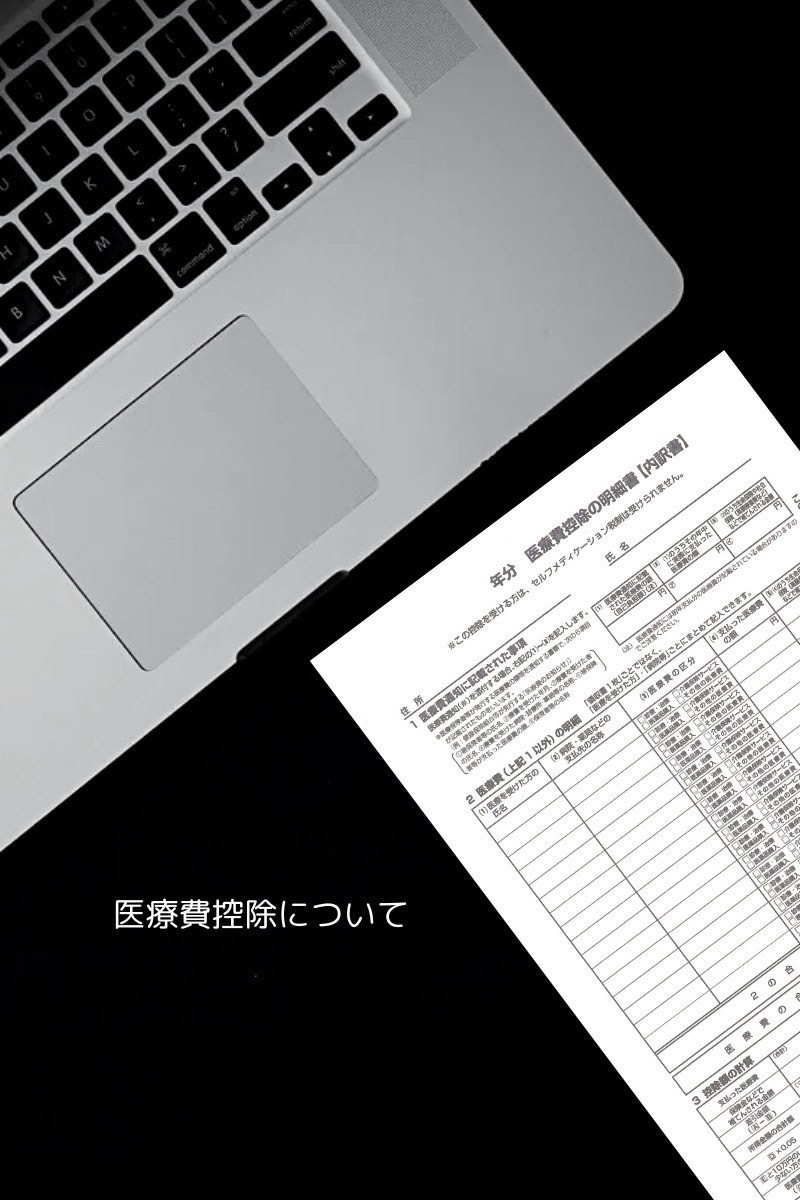
1月1日~12月31日までの1年間に、
また、
【医療費控除の対象となる医療費】
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価
(ただし、
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
(
(注)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、
(ただし、疲れを癒したり、
5 保健師、看護師、
(
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、
(注1)
(注2)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、
(3)身体障害者福祉法、
(4)
(注)介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、
10 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(
【医療費控除の計算方法】
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生
医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。
(年間の医療費の総額 - 保険金等で補填される金額) - 10万円(または所得の5%)
※最高控除額は200万円までです。
例えば、年間の医療費が50万円で、
(50万円 - 10万円)- 10万円 = 30万円
この30万円が所得控除され、税負担が軽減されます。
【医療費控除の手続き】
医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。
1. 必要書類の準備
• 医療費の領収書(病院・薬局など)
• 交通費の記録(通院日、経路、金額)
• 健康保険の給付明細書(高額療養費や出産育児一時金など)
• 源泉徴収票(給与所得者の場合)
2. 申告書の作成
• 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する
• 税務署で入手できる申告書に記入する
3. 税務署へ提出
• 確定申告期間(通常2月16日~3月15日)に提出
• e-Tax(電子申告)を利用することも可能
【セルフメディケーション税制との比較】
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、
※ 対象医薬品の範囲
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
具体的な対象医薬費品の一覧は、
(注) セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用である
〔ワンポイントアドバイス〕
どちらを選ぶべきか?
• 医療費が年間10万円以上の場合 → 医療費控除
• 医療費が少なく、市販薬の購入が多い場合 → セルフメディケーション税制
【医療費控除の注意点】
1. 領収書の保管が重要
• 申告時に提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。
2. 扶養家族の医療費も合算可能
• 生計を一にしている家族の医療費も含めて計算できます。
3. クレジットカード払いも対象
• 医療費をクレジットカードで支払った場合も控除対象です。
4. 会社員でも確定申告が必要
• 年末調整では医療費控除は適用されないため、
【まとめ】
医療費控除は、医療費負担を軽減できる重要な制度です。
また、
あなたへのおすすめ記事
-
-
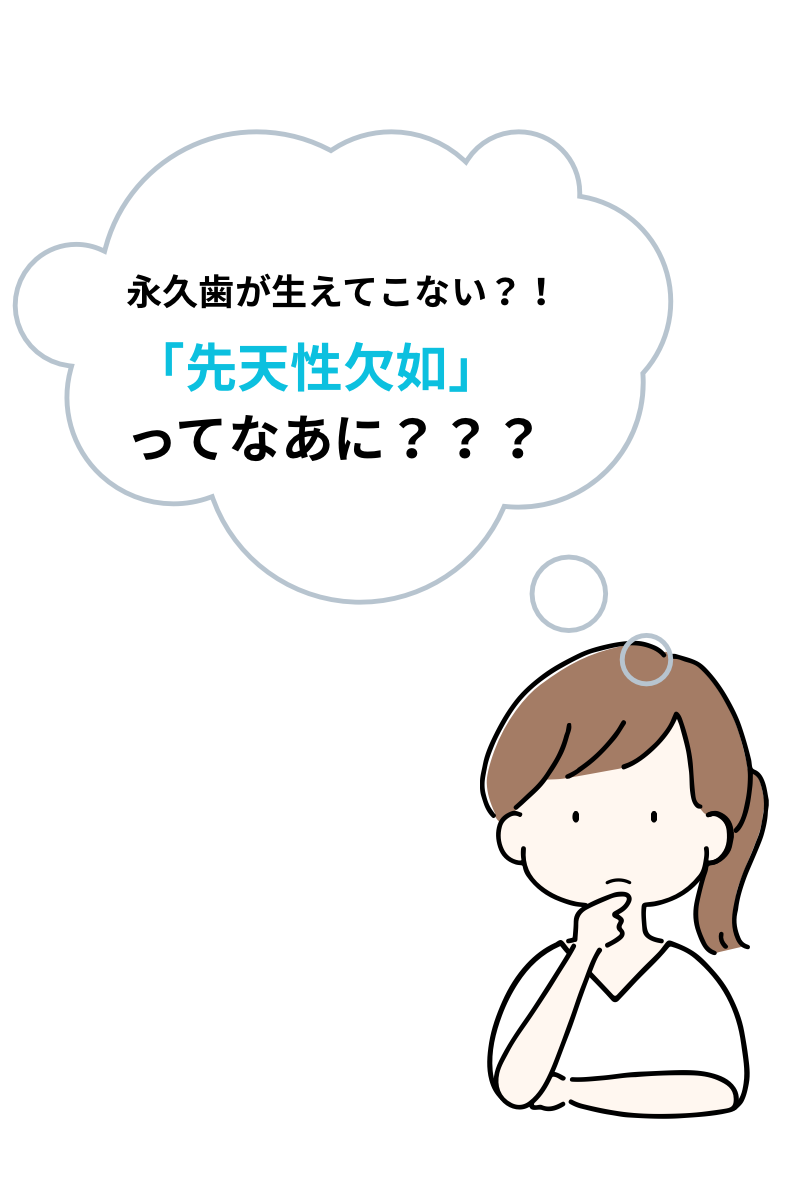
- 歯科治療について
- 【歯の先天性欠如とは?】生まれつき歯が足りないってどういうこと??
-
-
-
- 歯科治療について
- 歯並び・咬み合わせが悪いとどうなるの?~こころとからだの視点から~
-
-
-

- 歯科治療について
- こわくない治療の味方!笑気麻酔について
-
-
-

- スタッフブログ
- こども春まつり(リニューアルオープンイベント)を開催しました!
-
 0798-65-5611
0798-65-5611 電話する
電話する WEB予約
WEB予約



