ブログBlog

ブログ Blog
悪い癖ってどんなもの?
歯科治療について
2025/04/28

口腔習癖の詳細、影響、予防策、そして具体的な対処法について詳しく説明します。
「癖」という言葉は、ポジティブなものからネガティブなものまで、さまざまなタイプに使われます。たとえば、良い癖には早起きをする事や正しい箸の持ち方などがあり、悪い癖には猫背であることやいつも口がポカンと開いていることなどがあります。
ここでは、口腔の悪習癖について詳しくお話ししていきます。悪習癖とは、無意識または意識的に口腔内で行われる反復的な行動のことを指し、歯並びや健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらの習慣は、特に子供の発達段階で見られますが、大人にも見られることがあります。一般的な口腔習癖には以下のようなものがあります。
• 指しゃぶり(吸指癖):幼児が自分の指を吸う行為。
• 舌の前方突出:舌を前歯の間に押し出す行為。
• 舌の弄舌(ろうぜつ):舌を歯の裏側や歯間に押し付ける行為。
• 咬唇癖:唇を噛む行為。
• 口呼吸:鼻ではなく口で呼吸する習慣。
• 乳歯の早期脱落:乳歯が早期に抜けることによる後続の歯の位置異常。
• 頬杖(ほおづえ)癖:頬を手で支える行為。
• 爪噛み(そうこう):爪を噛む行為。
1. 指しゃぶり(吸指癖)
長期間続く指しゃぶりは、出っ歯や開咬などの原因となる可能性があります。改善方法は年齢にもよりますが、日中は両手を使う手遊びに誘ったり、手袋をはめる、苦味成分を配合した無添加マニキュアを塗るなどがあります。またそのお子さんの理解度に合わせて、なぜ指しゃぶりをやめた方がいいのかこのまま続けてしまうとどうなるかなどを優しく説明し、『〇〇迄にやめようね』など計画的に進めることも大切です。無理に止めさせようとせず、吸っていない時に褒めるなどのポジティブな強化を行うと効果的です。
2. 唇をかむ(咬唇癖)
唇を噛む癖は、出っ歯の原因となります。この習慣を改善するためには、子どもに唇を噛むことが歯並びに与える影響を説明し、注意深く見守りながら、必要に応じて歯科医師の指導を受けることが重要です。 咬唇癖は、緊張や不安やストレスなど精神的な事が原因となる場合もある為、その辺りの考慮も必要です。下唇を咬む癖は、唇が上下の前歯の間を頻繁に出入りすることによって前歯に圧がかかり、下顎前歯が舌側へ倒れたりして、前歯の咬み合わせに隙間が生じます。
3. 爪かみ(咬爪癖)
爪を噛む癖は指しゃぶりと同様に、上顎前歯を前に出す力が下顎前歯を内に倒す力がかかり、出っ歯になってしまいます。この習慣を改善するために、歯並びが悪くなる事を伝え、爪を咬んだ時に注意を促す事が大切です。爪を短く切ったり、指の爪に苦いマニキュアを塗るなどの方法が効果的です。
4. 舌突出癖
食べ物を飲み込む際に舌を前に出す癖は、歯並びに影響を及ぼします。改善方法として、舌の正しい位置や飲み込み方を教えるトレーニングや、マウスピースを使用して舌の位置を矯正する方法があります。 舌で歯を押す癖があると、その舌圧で歯列が外に広がる為、咬んでも前歯が閉じない開校や空隙歯列のすきっ歯になります。
5. 口呼吸
口呼吸は、顎の形や舌の位置に影響を与え、だんだんと歯並びや咬み合わせにまで繋がってしまう可能性があります。口呼吸により口周りの口輪筋や頬の筋力低下、口を閉じる力が衰えたりして、前歯を内側に抑える力が弱まったり、顎の骨の成長が妨げられたりします。改善するためには、鼻呼吸を促進するトレーニングや、鼻づまりの解消などが効果的です。
6. 頬杖(ほおづえ)
頬杖をつく習慣は、顔の歪みや歯並びに影響を及ぼすことがあります。頬杖をつくと、顎に頭の重さが加わり下顎が後退します。下顎を片方から支えるような頬杖をつくと、歯並びが内側方向にずれてしまい、左右非対称な変形した歯列となります。この習慣を改善するためには、頬杖が歯並びに与える影響を理解し、意識的に避けるよう心がけることが重要です。
7. うつ伏せ寝、横向き寝
うつ伏せや横向きで寝る習慣は、歯並びや顎の発達や顔の歪みに影響を及ぼす可能性があります。改善するためには、なるべく仰向け寝るように促す工夫が必要です。 上の顎のバランスが崩れると咬み合わせが逆になる反対咬合や、顎が横にずれる顎関節症といった症状に繋がってしまうこともあります。
改善のための一般的なアプローチ
• 意識づけ: 悪習癖が歯並びや健康に与える影響を理解し、意識的に改善しようとする姿勢が重要です。
• ポジティブな強化: 良い行動を取った際に褒めるなど、ポジティブなフィードバックを行うことで、習慣の改善を促進します。
• 専門家のサポート: 改善が難しい場合や習慣が定着している場合は、歯科医師や専門家の指導を受けることが効果的です。
これらの方法を試みても改善が見られない場合や、習慣が長期間続いている場合は、歯科医院での専門的な治療や指導を受けることをおすすめします。
2. 口腔習癖が及ぼす影響
これらの習慣が長期間続くと、以下のような歯や口腔の問題を引き起こす可能性があります:
• 歯並びの乱れ:歯が適切な位置に配置されず、出っ歯や受け口になることがあります。
• 噛み合わせの問題:上下の歯が正しく噛み合わず、食事や発音に支障をきたすことがあります。
• 口腔機能の低下:舌や唇の筋肉の発達に影響を及ぼし、口腔機能全般の低下を招くことがあります。
• 発音障害:口腔内の構造的な問題により、正しい発音が難しくなることがあります。
3. 口腔習癖の予防と対策
口腔習癖による影響を最小限に抑えるため、以下の予防策や対処法が効果的です:
• 早期の認識と介入:子供が習癖を持っている場合、早期に気づき、適切な対策を講じることが重要です。
• 専門家の相談:歯科医師や小児歯科医に相談し、専門的なアドバイスや治療を受けることが推奨されます。
• 習慣の置き換え:指しゃぶりなどの習慣を他の安全な行動に置き換える方法を検討します。
• 口腔周囲の筋肉トレーニング:舌や唇の筋肉を強化するエクササイズを行い、正常な口腔機能を促進します。
• 家族や周囲のサポート:家族や周囲の人々が協力し、子供が習癖を改善できるよう支援することが重要です。
4. まとめ
口腔習癖は、幼少期に見られることが多いですが、放置すると歯や口腔の問題を引き起こす可能性があります。早期の認識と適切な対策が、健康な口腔環境を維持するために不可欠です。お子さまの口腔習癖が気になる場合や、改善が難しい場合は、専門の歯科医師に相談することを強くおすすめします。
以上が口腔習癖に関する詳細な情報です。ご質問やさらに詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお知らせください。
「癖」という言葉は、
ここでは、口腔の悪習癖について詳しくお話ししていきます。
• 指しゃぶり(吸指癖):幼児が自分の指を吸う行為。
• 舌の前方突出:舌を前歯の間に押し出す行為。
• 舌の弄舌(ろうぜつ):舌を歯の裏側や歯間に押し付ける行為。
• 咬唇癖:唇を噛む行為。
• 口呼吸:鼻ではなく口で呼吸する習慣。
• 乳歯の早期脱落:
• 頬杖(ほおづえ)癖:頬を手で支える行為。
• 爪噛み(そうこう):爪を噛む行為。
1. 指しゃぶり(吸指癖)
長期間続く指しゃぶりは、
2. 唇をかむ(咬唇癖)
唇を噛む癖は、出っ歯の原因となります。
3. 爪かみ(咬爪癖)
爪を噛む癖は指しゃぶりと同様に、
4. 舌突出癖
食べ物を飲み込む際に舌を前に出す癖は、
5. 口呼吸
口呼吸は、顎の形や舌の位置に影響を与え、
6. 頬杖(ほおづえ)
頬杖をつく習慣は、
7. うつ伏せ寝、横向き寝
うつ伏せや横向きで寝る習慣は、
改善のための一般的なアプローチ
• 意識づけ: 悪習癖が歯並びや健康に与える影響を理解し、
• ポジティブな強化: 良い行動を取った際に褒めるなど、
• 専門家のサポート: 改善が難しい場合や習慣が定着している場合は、
これらの方法を試みても改善が見られない場合や、
2. 口腔習癖が及ぼす影響
これらの習慣が長期間続くと、
• 歯並びの乱れ:歯が適切な位置に配置されず、
• 噛み合わせの問題:上下の歯が正しく噛み合わず、
• 口腔機能の低下:舌や唇の筋肉の発達に影響を及ぼし、
• 発音障害:口腔内の構造的な問題により、
3. 口腔習癖の予防と対策
口腔習癖による影響を最小限に抑えるため、
• 早期の認識と介入:子供が習癖を持っている場合、早期に気づき、
• 専門家の相談:歯科医師や小児歯科医に相談し、
• 習慣の置き換え:
• 口腔周囲の筋肉トレーニング:
• 家族や周囲のサポート:家族や周囲の人々が協力し、
4. まとめ
口腔習癖は、幼少期に見られることが多いですが、
以上が口腔習癖に関する詳細な情報です。
|
ReplyForward
|
あなたへのおすすめ記事
-
-

- 歯科治療について
- 子どもの過蓋咬合って何?
-
-
-

- 歯科治療について
- 小児矯正はいつから始めるべき? ~後悔しないためのタイミングと考え方~
-
-
-

- 歯科治療について
- 赤ちゃんから始めよう!歯と骨の健康を守るフッ素
-
 電話する
電話する WEB予約
WEB予約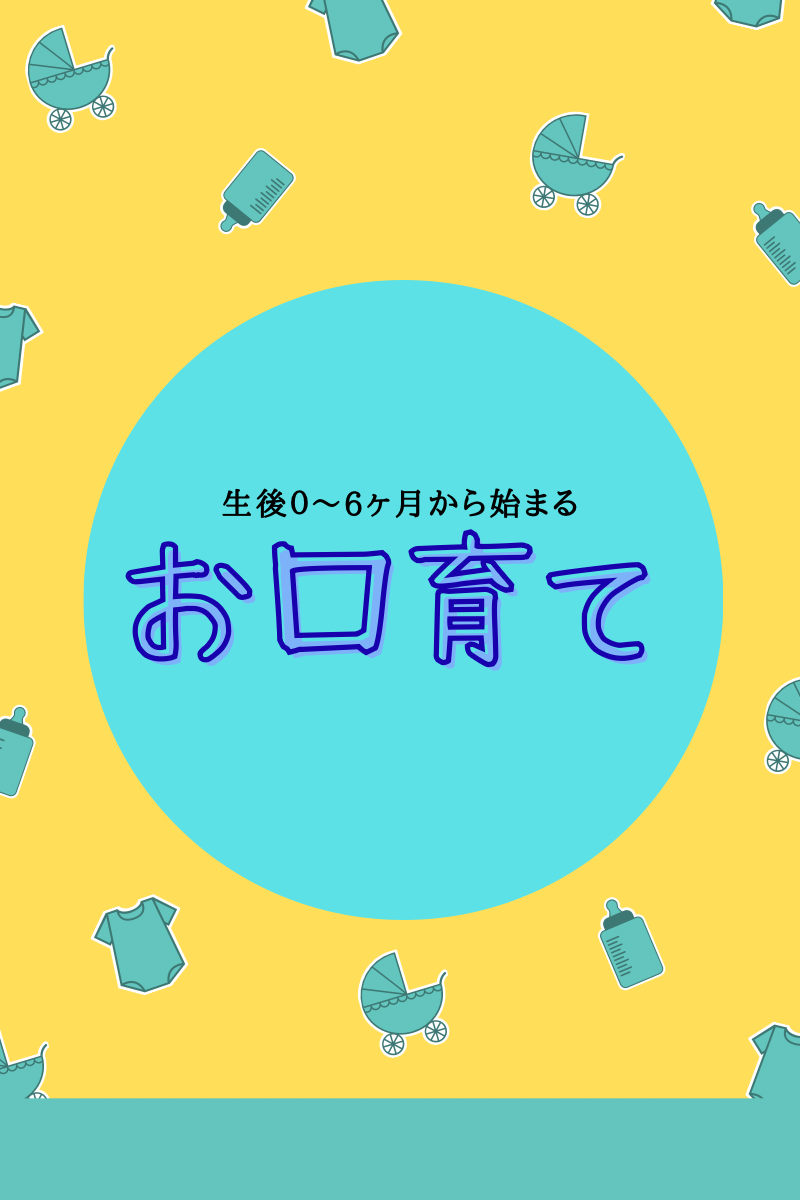


 0798-65-5611
0798-65-5611
